卵ってたしか一日3個までしか食べられないんだっけ?
かなり前はそういう噂はありましたね。しかし、現在では
違った見解が厚生労働省から提言されています。
そうなんだ。じゃあ何個までなら良いのだろう・・・?
それではこの記事を読んで勉強しましょう!
卵とコレステロールの関係について、近年の科学的見解や厚生労働省の方針は大きく変化しています。「卵は1日1個まで」「コレステロールが高い人は卵を食べてはいけない」といった情報に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。しかし、現在では食事から摂るコレステロールの影響は限定的であり、エビデンスに基づく論文もその見解を後押ししています。この記事では、卵の摂取が本当に血中コレステロールを上げるのか、健康な人やコレステロールが高い人は卵を1日何個までなら食べられるのか、また「卵とコレステロールは関係ない」とされる理由などについて、厚生労働省の見解や最新の研究をもとに丁寧に解説いたします。さらに、卵に含まれる栄養素がコレステロール値を下げる可能性についてもご紹介します。
- 卵の摂取がコレステロールに与える影響
- 厚生労働省の卵に関する公式な見解
- 卵の摂取制限が不要とされる理由
- 健康状態に応じた卵の適切な摂取量
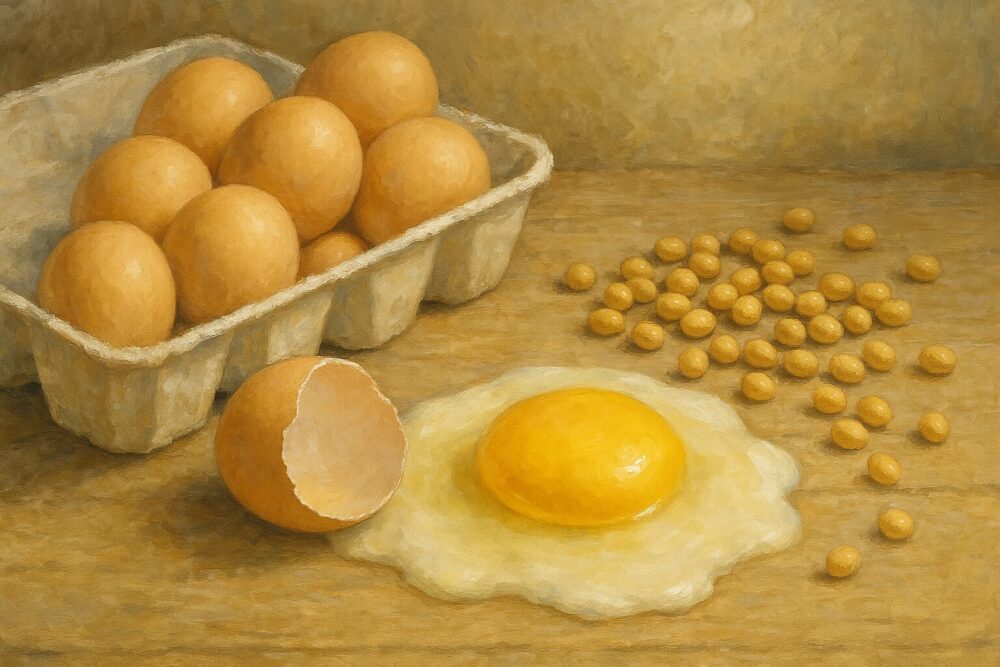
卵のコレステロールに関する厚生労働省の見解とは?
コレステロールが高い人は卵を食べてはいけない?
卵を避けるべきとされてきた背景には、「卵にはコレステロールが多く含まれている」という事実があります。ただし、近年の研究では、食事から摂るコレステロールが血中コレステロールに与える影響は人によって異なり、一概に卵を制限すべきとは言えないことが分かってきました。つまり、コレステロール値が高い人でも、卵を完全に避ける必要はない場合があります。
例えば、健康な人であれば1日1〜2個の卵を食べても問題ないとする研究もあり、個人差はあるものの、必ずしも禁止する必要はないという考え方が主流になりつつあります。一方で、すでに高コレステロール血症と診断されている人は、医師の指導のもとで摂取量を調整することが重要です。卵以外の食事や生活習慣も血中コレステロールに影響を与えるため、総合的な対策が求められます。
卵を食べるとコレステロール値は上がる?
かつては「卵を食べるとコレステロール値が上がる」と広く信じられていましたが、最近の科学的見解ではその関係性は限定的であるとされています。これは、食事から摂取するコレステロールが血中コレステロールに与える影響が、思ったよりも小さいという研究結果が増えているためです。
たとえば、健康な人が1日1個の卵を食べても、血中コレステロールが大きく上がるとは限りません。体にはコレステロールを調整する仕組みがあり、食事から多く摂取すると、肝臓での合成が自然と減ることが知られています。ただし、すでに脂質異常症などの持病がある人や、コレステロールに対して感受性が高い人は注意が必要です。個々の体質や健康状態に応じた食事管理が欠かせません。
卵は1日1個までというデマは本当?
「卵は1日1個まで」という情報は、かつての栄養指導の影響で広まりました。これは1970〜1980年代に提唱されたもので、当時は食事由来のコレステロールが血中に直接影響を及ぼすと考えられていたためです。しかし、現在ではこの制限は科学的根拠に乏しいという見解が広がっています。
現在の栄養学では、卵の摂取量に厳密な上限を設けていない国も多く、日本でも厚生労働省の食事摂取基準には卵の個数制限は明記されていません。また、卵は良質なたんぱく質やビタミン、ミネラルを豊富に含んでおり、むしろ健康維持に役立つ食材とされています。ただし、食生活全体のバランスを考慮しながら適量を守ることが大切です。習慣的に過剰摂取しなければ問題ないと考えられています。

卵のコレステロールは関係ないという説の根拠
「卵のコレステロールは関係ない」とされる根拠は、近年の大規模な疫学研究にあります。これらの研究では、卵の摂取と心血管疾患やコレステロール値の直接的な因果関係が明確には見られなかったと報告されています。つまり、卵をよく食べる人が、必ずしも心臓病や動脈硬化になりやすいとは限らないのです。
このような結果が出る背景には、人体が持つコレステロール調節機能が関係しています。食事で摂るコレステロールが増えると、体は自動的に体内での合成量を減らすため、血中濃度は一定に保たれる仕組みがあります。もちろん、これは全ての人に当てはまるわけではなく、個人差は存在します。したがって、卵がコレステロールに悪いという考え方は、現在では必ずしも正しいとは言えません。
エビデンスの紹介
卵とコレステロールに関する科学的エビデンスは、過去数十年にわたり多数発表されています。中でも注目すべきは、アメリカやヨーロッパの大規模な前向きコホート研究です。これらの研究では、日常的に卵を食べる人と、ほとんど食べない人の健康状態を比較した結果、心血管疾患の発症率に有意な差が見られなかったというデータが蓄積されています。
さらに、2020年代に入ってからのメタアナリシスでも、卵の摂取がコレステロール値に与える影響は限定的であり、1日1~2個であればリスクは高まらないとされています。これらのエビデンスは、従来の「卵は控えるべき」という考えに再考を促すものとなっています。ただし、基礎疾患を持つ方は、個別に医師の判断を仰ぐことが望ましいとされています。
論文に見る最新研究
最新の研究では、卵と心血管リスクの関連性を評価した論文が多く発表されています。特に信頼性の高い査読付きの医学誌では、食事からのコレステロール摂取と血中脂質との関係を慎重に分析した結果、「卵の摂取によって重大な健康リスクが増加するとは言えない」と結論づけているものが多く見られます。
例えば、2019年に発表された中国の10万人以上を対象にした研究では、1日1個の卵を食べているグループの方が、心血管疾患のリスクがやや低かったという結果も報告されています。また、同様の結果はアメリカやヨーロッパの研究でも確認されており、卵は中程度の量であれば健康的な食生活に組み込めるとする見解が主流です。こうした論文は、現在の栄養ガイドラインの見直しにも大きな影響を与えています。
卵のコレステロールに関する厚生労働省の推奨

厚生労働省が示す卵の栄養価の評価
厚生労働省は卵を「栄養価が非常に高い食品」と位置づけており、健康的な食生活を支える食品の一つとして推奨しています。卵は、たんぱく質、ビタミンB群、脂溶性ビタミン(A・D・E)やミネラルを豊富に含んでおり、特に必須アミノ酸のバランスが良いことが特徴です。
また、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、コレステロールの摂取上限が撤廃されており、卵の摂取量についても明確な制限は設けられていません。これは、最新の科学的知見に基づき、食事性コレステロールと健康リスクの直接的な関連が限定的であると考えられているためです。ただし、卵は脂質も含むため、他の高脂肪食品と併せて過剰摂取にならないように気をつける必要があります。食生活全体のバランスを整えた上で、卵は有効に活用できる食材です。
コレステロールが高い人は卵1日何個?
コレステロール値が高めの人が卵を1日に何個まで食べても良いかは、個人の体質や健康状態によって異なります。ただし、一般的なガイドラインでは「1日1〜2個程度」であれば多くの場合問題はないとされています。特に、卵の摂取だけがコレステロール値を決定づける要因ではないことが近年の研究で明らかになってきました。
例えば、飽和脂肪酸の摂りすぎや運動不足、喫煙、ストレスなども血中コレステロールに大きく影響します。したがって、卵の個数だけに注目するのではなく、生活全体の見直しが重要です。医師や管理栄養士の指導を受けつつ、自身の体調や血液検査の結果をもとに摂取量を調整するのが安全です。習慣的に食べるのであれば、1日1個を目安とするのが無難なラインでしょう。
コレステロールと摂り過ぎるとどうなるのか
コレステロールは体に必要な脂質であり、ホルモンや細胞膜の構成にも関与しています。ただし、血中のコレステロールが過剰になると、動脈硬化の原因となり、心筋梗塞や脳梗塞などのリスクが高まるとされています。特にLDLコレステロール(いわゆる悪玉コレステロール)が増えすぎると、血管内に脂肪が蓄積されやすくなります。
このため、コレステロール値が高い人は、動物性脂肪や加工食品の摂取量を見直すことが求められます。なお、コレステロール自体は体内で生成されているため、食事から摂り過ぎた場合は合成量が減る仕組みもありますが、それでも感受性が高い人ではコントロールが難しくなることも。自覚症状が出にくいため、定期的な健康診断による数値チェックが重要です。

卵1日2個は食べても大丈夫?
多くの研究結果やガイドラインでは、健康な成人が卵を1日2個食べることについて、リスクは非常に低いとされています。特に、全体の食事バランスが良好であれば、卵2個の摂取が心疾患リスクの上昇に直結する可能性は低いというのが主流の見解です。
例えば、アメリカの栄養ガイドラインでも「1日2個までの卵摂取は健康的な食事の一部」として容認されています。また、卵には食物繊維やビタミンC以外のほとんどの栄養素が含まれており、栄養補給にも適した食品です。ただし、卵を調理する際にバターやマヨネーズを多用すると、総脂肪量が増えるため注意が必要です。ゆで卵や蒸し卵のようなシンプルな調理法で取り入れると、健康的に楽しむことができます。
コレステロールを下げる効果があるという情報も
意外に思われるかもしれませんが、卵にはコレステロールを直接「下げる」可能性があるという報告もあります。特に注目されているのが、卵黄に含まれる「レシチン」という成分です。レシチンには脂質の代謝を助ける働きがあり、血中のLDLコレステロールを減少させる方向に働く可能性があるとされています。
また、卵白部分は脂質がほとんど含まれておらず、良質なたんぱく質源として知られています。コレステロール値が気になる方は、卵黄の摂取量を調整することでバランスを取る工夫も可能です。もちろん、これだけで大きな改善が見込めるわけではありませんが、他の健康的な食品と組み合わせることで、血中脂質の管理に貢献する可能性があります。単純に「卵=悪」と考えるのではなく、成分の役割を理解したうえで上手に活用していくことが求められます。
コレステロールと肥満の関係性
コレステロールと肥満は直接的な因果関係があるわけではありませんが、両者は生活習慣病のリスク要因として密接に関連しています。特に、内臓脂肪型肥満の人は、LDLコレステロールが増加しやすく、逆に善玉のHDLコレステロールが減少する傾向にあります。これにより、動脈硬化のリスクが高まりやすくなるのです。
また、過剰なエネルギー摂取や運動不足は、肥満とともに血中脂質のバランスを悪化させる原因となります。卵そのものは肥満の原因にはなりにくい食品ですが、過剰なカロリー摂取や不規則な生活と組み合わさることで、健康リスクが高まります。したがって、卵の摂取量だけでなく、食生活全体と体重管理を意識することが、コレステロール対策としては欠かせません。
厚生労働省の情報から読み解く卵とコレステロールの関係についてのまとめ
- 卵にはコレステロールが多く含まれているが、摂取による影響は個人差がある
- 近年では卵を完全に避ける必要はないという見解が主流になりつつある
- 健康な人が1日1~2個の卵を食べても問題ないとされる研究が増えている
- すでに高コレステロール血症と診断されている人は医師の指導が必要
- 「卵を食べるとコレステロール値が上がる」という考えは古い常識となっている
- 体内にはコレステロールを調整する仕組みがあるため摂取の影響は限定的
- 卵は良質なたんぱく質やビタミン、ミネラルが豊富な栄養価の高い食品である
- 「卵は1日1個まで」は過去の栄養指導に基づく誤った情報とされている
- 日本の食事摂取基準では卵の摂取個数に明確な上限は設けられていない
- 最新の研究では卵の摂取と心血管疾患との因果関係は明確でないとされる
- 食事性コレステロールと健康リスクの関連は限定的という見解が増えている
- 中国の研究では卵を食べる人の方が心疾患リスクが低い傾向も報告されている
- 厚生労働省は卵を健康的な食生活に役立つ食品として評価している
- 卵に含まれるレシチンは脂質代謝を助け、LDLコレステロールの低下に関与する可能性がある
- 卵の摂取数よりも生活習慣全体を見直すことがコレステロール管理には重要
コメント