最近は本物そっくりな卵があるみたいだけどどんな商品なんだろうか
キューピーが発売しているシリーズで、いろんなバリエーションもあって注目されていますよ。
どんなものなのか気になる!教えてください。
卵アレルギーやヴィーガン対応の食品が求められる中、キューピーが開発した卵もどきが注目を集めています。植物性原料を使い、本物の卵のような見た目や食感を再現したこの代替卵は、家庭用だけでなく、業務用としても幅広く活用されています。スクランブルエッグ風やゆで卵風などのバリエーションも豊富で、使い勝手の良さが特徴です。
この記事では、キューピー製品の特長や原材料、安全性の考え方に加え、半熟タイプやゆで卵風タイプの活用方法も紹介します。きみぷちやコンビニ向け商品の情報、さらに業務用商品の導入を検討している方にも役立つ内容です。
代替卵に関する疑問や不安を持っている方にとっても、安心して使える選択肢のひとつとして理解が深まるはずです。
- キューピーの卵もどき「HOBOTAMA」の特徴と開発背景
- 原材料や製造技術に関する基本情報
- 商品の種類や調理・活用方法
- 保存方法や購入手段、利用時の注意点
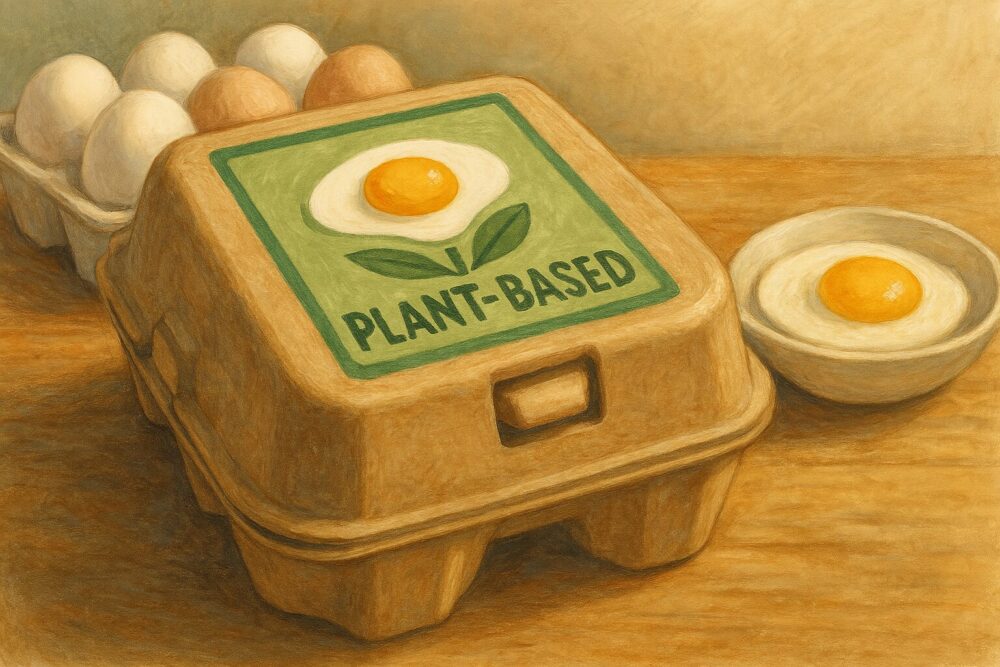
目次
- 1 キューピーの卵もどきとは?基本情報を解説
- 1.1 卵もどきの開発背景とは?キューピーの取り組み
- 1.2 卵もどきの特長:原材料や製造技術について
- 1.3 卵もどきの開発背景とは?キューピーの取り組み
- 1.4 卵もどきの特長:原材料や製造技術について
- 1.5 キューピーの卵もどきが注目される理由
- 1.6 ゆで卵もどきとしての活用法とサラダへの応用法
- 1.7 スクランブルエッグ風に使える卵もどきの魅力
- 1.8 代替卵を活かしたレシピ:オムレツやマヨネーズ
- 1.9 きみぷちの味や食感のレビュー
- 1.10 きみぷちの価格と保存方法
- 1.11 きみぷちの購入方法と配送情報
- 1.12 卵もどきの特定原材料や大豆成分について
- 1.13 卵もどき日本製品の安全性とアレルギー対応
- 1.14 卵もどきの食品加工技術とその利点
- 1.15 ゆで卵風、半熟卵風などの種類の比較
- 2 キューピーの卵もどきと他の代替食品との違い
キューピーの卵もどきとは?基本情報を解説
卵もどきの開発背景とは?キューピーの取り組み
キユーピーが卵もどきの開発に取り組んだ背景には、「多様な食のニーズに応えたい」という強い想いがありました。近年、卵アレルギーやヴィーガンの人が増加する中で、動物性原料を使わない代替食品の需要が高まっています。その流れを受け、2019年に新設された「新領域創造部」では、従来の枠を超えた商品開発がスタートしました。
開発のヒントとなったのは、京都の伝統食品「湯葉」です。旅行先で体験した湯葉丼のとろっとした食感が、スクランブルエッグ風商品「ほぼたま」の原型となりました。試作は139回にも及び、社内でも前例のない挑戦だったため、完全に手探りで進められたそうです。
キユーピーは長年、卵に関するノウハウを培ってきました。その知見を活かしつつ、「卵を使わない卵料理」という矛盾に向き合いながら新たな価値を生み出しています。
卵もどきの特長:原材料や製造技術について
キユーピーの卵もどき「HOBOTAMA(ほぼたま)」は、動物性原料を一切使用していないのが最大の特長です。原材料の中心は豆乳や脱脂アーモンドパウダーなどの植物性素材で、味・色・食感のすべてを“卵風”に再現しています。この工夫によって、卵アレルギーのある方やヴィーガンの方でも安心して食べられる代替卵が実現しました。
製造技術の面では、加熱しても滑らかさを保つ工夫や、ふわとろの食感を再現するための配合比の調整がポイントです。試作段階では加熱によって固くなりすぎたり、水っぽくなったりする問題が多く、一つ一つ微調整を重ねて完成された製品です。
ただし、一般的な卵と比べると風味が若干異なるため、料理によっては使い方を工夫する必要があります。とはいえ、加熱調理や湯煎のみで使える利便性は高く、現代の忙しいライフスタイルにも適した製品と言えるでしょう。
卵もどきの開発背景とは?キューピーの取り組み
キユーピーが卵もどき「HOBOTAMA(ほぼたま)」を開発した背景には、食の多様化とアレルギー対応の必要性がありました。近年、卵アレルギーを持つ人や、動物性食品を避けるライフスタイルが増えてきたことを受け、新しい食の選択肢が求められています。そこで、長年卵製品を扱ってきたキユーピーが、卵を一切使わない“ほぼ卵”に挑戦しました。
この製品は、単にアレルギー対策やヴィーガン向けというだけでなく、「おいしい代替食品」を目指したことが大きな特徴です。開発のヒントとなったのは京都の名物である湯葉。湯葉のなめらかでとろっとした食感がスクランブルエッグのように応用できると考えたのがスタートでした。
開発者は子どもの頃から卵料理に親しんでおり、そのこだわりが「ふわとろ感」を生み出す原動力となりました。試作は139回にも及び、完成まで約2年を要したとされています。
卵もどきの特長:原材料や製造技術について
キユーピーの卵もどき「HOBOTAMA」は、植物性の原材料だけで卵のような食感や見た目を再現しているのが最大の特長です。主に豆乳やアーモンドパウダーなどを使い、加熱後にふんわりとした質感が出るよう製法に工夫を凝らしています。
製造では、食感・色・風味の再現性が重視されています。卵料理特有の「とろっと感」「コク」「焼き色」などを、動物性素材なしで再現するのは難しく、何度も調整が重ねられました。その結果、調理後でもべたつかず、誰でも手軽に扱える冷凍食品として製品化に成功しました。
ただし、風味やコクの面で本物の卵とまったく同じというわけではないため、料理によってはスパイスや調味料で補う必要があります。

キューピーの卵もどきが注目される理由
HOBOTAMAが注目を集めているのは、アレルギー対策食品の枠を超えた完成度の高さにあります。日本国内では、代替卵の開発はまだ初期段階にあり、「卵もどき」でここまでの味・見た目・食感を実現した例は多くありません。
また、冷凍品でありながら湯煎や解凍だけで調理ができる手軽さも魅力の一つです。特に業務用としては、調理スタッフの技術に左右されず、誰でも一定の品質で提供できる安定性が評価されています。
卵を使わない「エッグケアマヨネーズ」など、既存の卵製品と並ぶラインナップの中で、HOBOTAMAは次世代の“卵代替食品”として注目されています。
ゆで卵もどきとしての活用法とサラダへの応用法
ゆで卵の代わりとしても、卵もどきは非常に便利です。**見た目の白身と黄身のコントラストがしっかり再現されており、サラダに加えると彩りが格段に良くなります。**実際、半分にカットするだけで断面もリアルなゆで卵にそっくりなため、見た目重視の料理でも違和感がありません。
また、味自体が控えめな設計になっているため、ドレッシングや塩などとの相性が良く、サラダに加えるだけで簡単に満足度の高い一皿になります。ゼラチンや油分の工夫によって、加熱しても崩れにくく、サンドイッチやポテトサラダなどにも応用可能です。
一方で、日持ちの面では冷蔵保存が必要であるため、使用する分だけ解凍するなどの工夫が求められます。
スクランブルエッグ風に使える卵もどきの魅力
スクランブルエッグ風に仕上がった卵もどきは、ふわとろ食感が魅力です。火加減や調理技術が不要で、湯煎だけでプロ級の仕上がりが可能なのは大きなメリットです。特に、業務用としては、オペレーションの簡略化に直結するため、忙しい現場に重宝されています。
ヴィーガンや卵アレルギーを持つ方に向けて、スクランブルエッグが提供できるという点でも、飲食店などから注目されています。豆乳や植物性オイルがベースとなっており、タンパク質源としても一定の栄養価があります。
味わいはあっさりしており、調味料やトッピングのアレンジも自在です。その一方で、卵のコクを求める方にはやや物足りなさを感じる可能性もあるため、工夫した味付けが推奨されます。
代替卵を活かしたレシピ:オムレツやマヨネーズ
代替卵はオムレツやマヨネーズ風の料理にも応用できます。**特に「HOBOTAMA 加熱用液卵風」は、火を通すことで固まり、オムレツや卵焼きに仕上げることが可能です。**焼き加減の調整で半熟風からしっかり焼きまで幅広く対応できます。
また、キユーピーでは卵不使用のマヨネーズタイプ「エッグケア」も展開しており、卵アレルギーの方でも安心してサラダやサンドイッチに使えるレシピが広がっています。味もマイルドで、従来のマヨネーズに遜色ない仕上がりです。
注意点としては、液卵風タイプは冷凍保存品のため、解凍・加熱の手順に従う必要がある点です。袋ごと電子レンジは不可なので、使用前に必ず解凍方法を確認しましょう。
きみぷちの味や食感のレビュー
「きみぷち」は、見た目も味も本物の卵黄そっくりで、多くの人が驚きを感じる加工品です。ゼラチンを使った独自の技術で、温めても崩れずぷるんとした食感をキープしています。口に入れた瞬間にトロリととろけ、まさに卵黄ソースのような風味が広がります。
味わいとしては、本物の卵黄よりもややマイルドで、しつこさがないのが特徴です。そのため、サラダやお弁当、洋食のトッピングにも使いやすく、見た目の演出にも優れています。
ただし、加熱のしすぎや冷凍状態での扱いには注意が必要で、破損する場合もあるため、調理時は丁寧に扱うことが求められます。
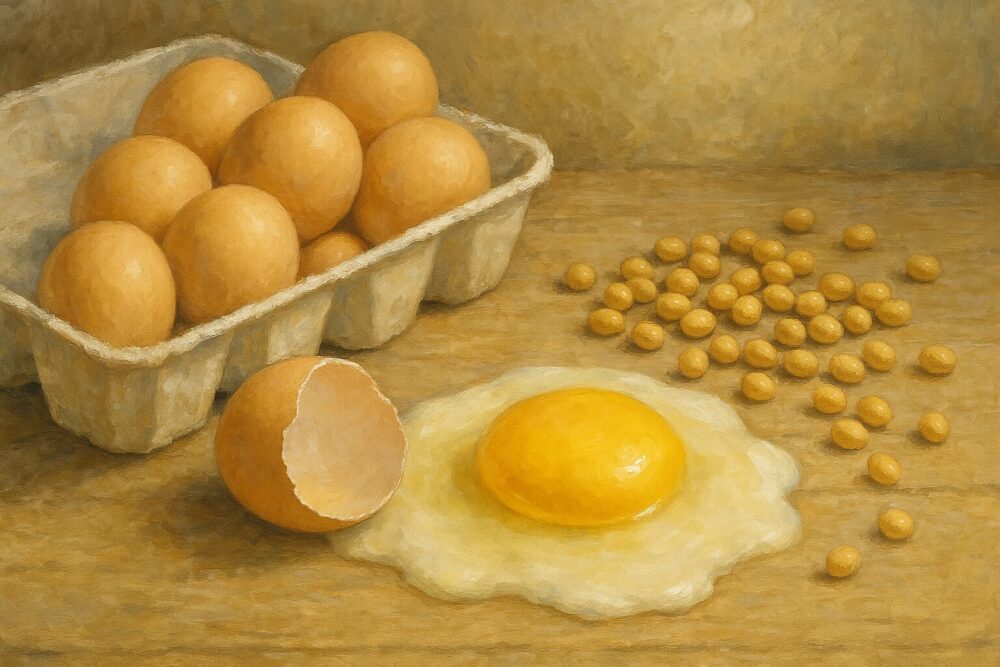
きみぷちの価格と保存方法
「きみぷち」は主に業務用として販売されているため、一般的なスーパーではあまり見かけませんが、ECサイトや業務用食品ルートで1パック数百円台で購入可能です。サイズや個数によって価格は異なりますが、コストパフォーマンスは高いといえます。
保存方法としては、冷蔵が基本です。冷凍すると食感が変化する可能性があるため、未開封状態での冷蔵保存が推奨されています。また、開封後はなるべく早く使い切ることが望ましく、トッピング用途であれば、1~2日以内に使い切ると風味や食感を損なわずに楽しめます。
業務用として導入する場合には、大量購入によるロス管理や保存環境の整備も重要となるため、導入前に保存スペースの確認をしておきましょう。
きみぷちの購入方法と配送情報
「きみぷち」は一般の小売店では流通していませんが、業務用食品を扱う通販サイトや、一部のキユーピー公式オンラインショップで取り扱いがあります。家庭用としてはまだ流通が限定的なため、入手の際はネット検索での在庫確認が必要です。
配送については、冷蔵商品であるためクール便で届くのが一般的です。配送エリアによっては配達日数がかかるため、余裕をもって注文することが大切です。また、まとめ買いによって送料が無料になるケースもあるため、必要な分を見積もって購入計画を立てると効率的です。
もし家庭用サイズが希望であれば、今後の市販化の動きにも注目しておくと良いでしょう。
卵もどきの特定原材料や大豆成分について
キユーピーの卵もどき製品の多くは、アレルギー対応を意識して設計されています。ただし、原材料として大豆やアーモンドなどが使用されているため、特定アレルゲンへの注意が必要です。製品によって使用原料は異なるため、購入時には成分表の確認が欠かせません。
例えば「ほぼたま スクランブルエッグ風」は豆乳ベース、「加熱用液卵風」はアーモンドパウダーが主成分となっています。これにより、卵を完全に除去しながらも、食感や風味を近づけることに成功しています。
一方で、大豆やナッツ類にアレルギーを持つ方にとっては注意が必要となるため、代替卵=完全な安全食品という認識ではなく、個々の体質に合わせて選ぶことが重要です。
卵もどき日本製品の安全性とアレルギー対応
国内メーカーが開発した卵もどきは、衛生面・製造環境ともに厳しい基準で管理されており、安心して口にできる品質を誇ります。特にキユーピーは長年にわたり卵加工を行ってきた実績があり、最新の衛生基準に基づいた工場で製造されています。
また、製品には特定原材料の表記が明記されており、アレルゲン表示も義務化に対応した仕様となっている点が評価されています。そのため、食物アレルギーを持つ子どもや高齢者にも配慮したメニュー作成がしやすくなっています。
ただし、全くの無添加というわけではなく、保存安定性や食感維持のために最低限の添加物を使用しているケースもあります。気になる方は詳細情報を確認した上で選択するとよいでしょう。

卵もどきの食品加工技術とその利点
卵もどき製品には、独自の加工技術が活用されています。例えば、豆乳やアーモンド粉などの植物性原料を安定した食感に仕上げるための加熱調整技術や、滑らかさを損なわない凍結方法などが挙げられます。これにより、湯煎や加熱だけで自然な「ふわとろ」感が再現できるのです。
この技術の利点は、調理現場における負担軽減です。卵を割る・混ぜる・火加減を調整するといった作業が不要になり、調理時間やロスが削減されます。また、卵殻の衛生リスクも回避できるため、病院や学校、介護施設などでも活用しやすい点が評価されています。
調理環境が整っていない場所でも簡単に取り扱えるため、業務用を中心に幅広く展開が進んでいます。
ゆで卵風、半熟卵風などの種類の比較
卵もどきには、「ゆで卵風」「半熟卵風」「液卵風」「スクランブル風」など多彩なバリエーションがあります。**ゆで卵風は、サラダや弁当のトッピングに最適で、見た目もリアルな断面が特徴です。**一方、半熟風はオムレツや丼物など、料理の中でとろっとした存在感を出すのに適しています。
スクランブルエッグ風は調理不要で、そのまま加熱してふわとろの食感が味わえるため、時短調理に向いています。液卵風タイプは火を通して固める調理に適しており、卵焼きやオムレツといった加熱料理にぴったりです。
それぞれの特徴を理解し、料理や用途に応じて選ぶことで、より満足度の高いメニュー作りが可能になります。
キューピーの卵もどきと他の代替食品との違い
液卵タイプと業務用商品の特徴
液卵タイプの卵もどきは、調理前の状態で卵のように使用できる点が大きな特長です。特に加熱調理で固まる性質を持っているため、オムレツや卵焼きなどの用途にぴったりです。
業務用商品としては、冷凍状態で納品されるため保存性が高く、必要な分だけ解凍して使える仕様になっています。これにより、食品ロスの削減にもつながります。また、同じ品質のものを誰でも簡単に作れる再現性の高さも、現場で高評価を得ている理由の一つです。
ただし、電子レンジ加熱ができないなど、調理法に制限がある製品もあるため、導入時には使用方法をしっかり確認することが必要です。
期間限定品や新商品の紹介
卵もどき市場はまだ新しい分野であるため、季節ごとの新商品や期間限定品も多く登場しています。たとえば、「カレーパン用のとろ〜り卵」や、「ひらけオムレツ」など、用途に特化した商品が話題を集めています。
これらの製品は、見た目や食感の演出に加えて、味わいにも季節感を取り入れており、イベントやフェアと組み合わせることで、消費者の興味を引くことができます。
ただし、期間限定品は生産数が限られているため、早めの注文が必要です。導入したい場合は、メーカーの情報発信やニュースリリースを定期的にチェックするのがおすすめです。

コンビニで購入できる卵もどき商品とは?
最近では、コンビニでも卵もどきを使った商品が少しずつ見かけられるようになってきました。**代表的なのは、半熟風のスライスたまごや、黄身風のトッピングがされたサラダなどです。これらの商品は、手軽に栄養を補給できるだけでなく、見た目の華やかさからも人気を集めています。
多くは「スノーマン」ブランドなど業務用系商品を活用しており、店舗によっては味付けや食感の違うタイプを取り扱っている場合もあります。ただし、日常的に買える商品はまだ限られているため、地域差や販売期間には注意が必要です。
近い将来、こうしたアイテムがもっと一般的になっていくと、選択肢も増えていくでしょう。
卵もどきを使ったコンビニサラダの魅力
コンビニのサラダに使用されている卵もどきは、彩り・味・ボリューム感を手軽に加えることができる点で非常に優秀です。とくに「きみぷち」や半熟風のスライスタイプは、見た目が鮮やかで食欲をそそります。
また、卵アレルギーのある方にとって、卵入りサラダは敬遠しがちですが、卵もどきなら安心して手に取ることができます。植物性由来の原料でつくられているものが多く、ヘルシー志向の人にもマッチしやすいのです。
日持ちや冷蔵保存性も高いため、利便性の高い商品として今後さらに普及していくことが期待されます。
卵もどきの商品展開と今後の可能性
卵もどき市場は、今後大きな広がりを見せる分野と考えられています。キユーピーをはじめとした大手食品メーカーが本格参入していることで、商品バリエーションも急速に増加中です。
現在は業務用が中心ですが、一般家庭向けの冷凍商品やレトルトタイプも少しずつ市販化されています。ヴィーガンやアレルギー対応食としての需要に加え、エコ志向の広がりも追い風となっています。
今後は、調理法の簡略化や味の改良などを通じて、より日常に溶け込んだ商品が登場するでしょう。
卵もどきの評価ポイントとユーザーの声
実際に卵もどきを使った人からは、「想像以上に本物に近い」「時短に役立つ」「子どもが喜んだ」などの声が多く聞かれます。とくにスクランブルエッグ風の「ほぼたま」は、簡単にプロのような仕上がりになる点が高評価を得ています。
一方で、「本物の卵ほどのコクがない」「調理法を間違えると崩れやすい」などの意見もあり、用途や期待に応じて評価が分かれる傾向があります。
総じて「便利」「安全」「時代に合っている」という意識が強く、今後の改良にも注目が集まっています。

業務用商品としての需要と評判分析
業務用市場においては、卵もどき製品が着実に支持を集めています。とくに人手不足や衛生管理が課題となる外食・中食業界では、「湯煎で完了」「殻処理が不要」といった利点が大きな武器となっています。
また、味の均一性が保てるため、料理人の技量に左右されずにクオリティを確保できるのも魅力の一つです。そのため、大手チェーン店や給食施設でも導入が進んでいます。
現時点ではコスト面のハードルもありますが、量産化が進めば価格も安定し、より多くの現場で活用されるでしょう。
卵もどきの評価をもとにした改良点
ユーザーの声を反映し、卵もどきは進化を続けています。味の深みや香りをより卵らしくする工夫や、加熱時の崩れにくさの改善など、課題を一つずつクリアしてきました。
近年では、冷凍耐性の向上やレンジ調理対応への開発も進められており、今後は家庭での利便性がさらに高まることが予想されます。また、見た目だけでなく「料理全体にどう馴染むか」という点も改良ポイントとして重視されています。
開発現場では、消費者のリアルな使用感が最も重要視されており、使いやすさの追求が進んでいます。
鶏卵との違い:味、食感、価格の比較
卵もどきは鶏卵とは異なる特徴を持っています。味はややマイルドでクセが少なく、料理に馴染みやすいのが特長です。一方、濃厚さや旨みの深みはやや劣るため、調味料や具材で工夫する必要があります。
食感については、スクランブル風や半熟風など、製品ごとに異なる工夫が施されていますが、本物の卵の弾力やとろみを完全に再現するのは難しいのが現状です。
価格面では、現時点ではやや高めに感じるかもしれませんが、保存性や時短性を加味すると十分コストに見合った価値があります。
他の代替食品との原材料や栄養価の違い
他の代替食品、たとえば大豆ミートや植物性ミルクと比べて、卵もどきは主に「食感の再現性」に強みがあります。原材料には豆乳・アーモンドなどが使われることが多く、脂質・タンパク質のバランスも良好です。
ただし、ビタミンやミネラルの量は鶏卵に比べると少なめなため、栄養補助食品としてよりも、アレルゲン対応・味の再現を重視した食品と捉えるのが正確です。
特定の栄養素が必要な場合は、別の食品と組み合わせて取り入れるのがよいでしょう。
持続可能性を考えた卵もどきのメリット
卵もどきは、動物性原料を使わないことで環境負荷を軽減できる点が注目されています。鶏の飼育に比べて水や飼料が不要で、温室効果ガスの排出も少ないとされています。
また、食料資源の多様化という観点でも、持続可能な社会に向けた選択肢の一つです。サステナブルな食生活を意識する人にとって、卵もどきは非常に有力な代替品となり得ます。
ただし、大豆やナッツなどの原料調達も今後の環境課題と直結してくるため、供給元や生産体制の透明性がさらに求められていくでしょう。
卵もどきの保存条件と注意点
卵もどきは冷凍または冷蔵保存が基本です。種類によって保存温度帯や賞味期限が異なるため、製品ごとに管理が必要です。特に液状タイプは冷凍状態で保存し、解凍後は数日以内に使い切ることが推奨されています。
また、再冷凍は食感や風味が劣化する原因となるため避けた方がよいでしょう。解凍時の水分の抜けやすさにも注意が必要で、ゆっくり冷蔵解凍すると品質を保ちやすくなります。
使用頻度や調理方法を考慮しながら、適切な保存計画を立てることがポイントです。

賞味期限を延ばす保存方法のコツ
卵もどきの賞味期限を長持ちさせるためには、未開封の状態での冷凍保存が最も効果的です。特に業務用パックは1食分ずつ小分けされていることが多く、必要な分だけ取り出して使うスタイルが便利です。
冷蔵保存の場合は、開封後なるべく早めに使い切ることが重要です。食品ロスを避けるためにも、計画的な使用と正確な解凍手順が欠かせません。
また、冷凍や解凍時の結露や温度変化にも注意を払いましょう。品質を保つためには温度管理が鍵となります。
冷凍保存や加熱調理での違いと注意点
卵もどき製品の多くは冷凍保存が可能ですが、**加熱調理の仕方によって風味や食感に差が出ることがあります。**たとえば、湯煎加熱とフライパン加熱では食感に微妙な違いが生じることがあります。
電子レンジでの加熱は禁止されている製品もあるため、パッケージの指示通りの調理方法を守ることが品質を損なわないコツです。
また、解凍後すぐに使用せず常温放置してしまうと、雑菌の繁殖や品質劣化の原因になるため注意が必要です。安全かつおいしく使うには、正しい調理と保存の両立が大切です。
- キユーピーは卵を使わない代替卵「HOBOTAMA(ほぼたま)」を開発
- 開発のきっかけは食の多様化とアレルギー対応ニーズの高まり
- 商品開発のヒントは京都の湯葉から得られた
- ふわとろ食感を目指し139回の試作を重ねて完成
- 原材料は豆乳やアーモンドパウダーなど植物性素材
- 動物性原料不使用でヴィーガンや卵アレルギーにも対応
- 湯煎や加熱だけで簡単に調理できる冷凍食品
- スクランブルエッグ風や液卵風など種類が豊富
- ゆで卵風タイプはサラダやサンドイッチに活用可能
- 味はマイルドでコクはやや控えめだが使いやすい
- 保存方法は冷蔵または冷凍で、製品ごとに異なる
- コンビニサラダや業務用弁当などにも採用が進む
- 評価は高く、使いやすさや調理の簡便さが好評
- マヨネーズ代替品「エッグケア」もラインナップにあり
- 環境負荷の少ないサステナブル食品としても注目されている
コメント